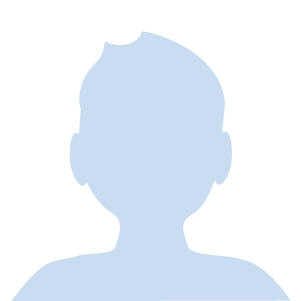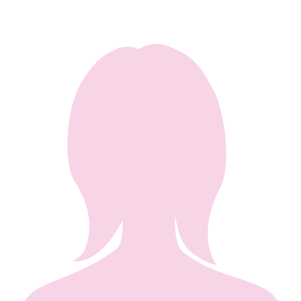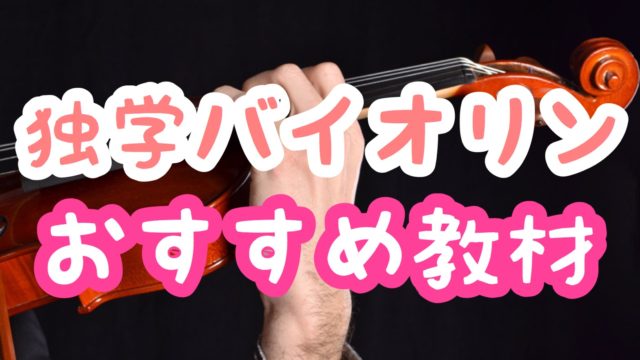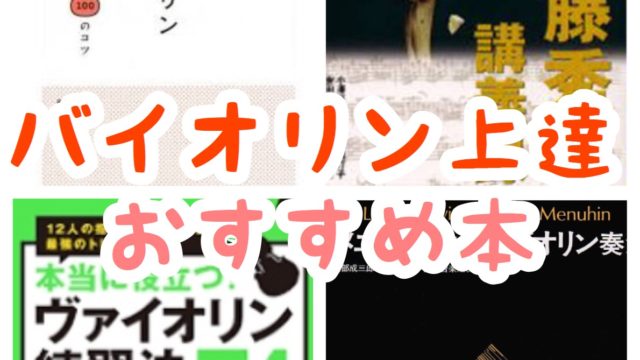この記事はバイオリンを演奏して生計を立てている、とあるバイオリニスト(@violin18media)が自身の経験談を元に作成したものです。
という疑問にお答えします。
Contents
ビブラートの種類
ビブラートは実はかけ方に3つの種類があります。
・指でかけるビブラート
・手首でかけるビブラート
・腕でかけるビブラート
具体的に説明していきます。
指でかけるビブラート
指でかけるビブラートは指の第一関節を伸ばしたり曲げたりしてビブラートをかけます。主に速いビブラートをかける際に使うことが多いのですが、人によって第一関節が動く人と動かない人がいるようですので、無理に指のビブラートをかける必要はありません。
私は指のビブラートは全く使っていませんし、生徒にも教えていません。
手首でかけるビブラート
手首でかけるビブラートは手首を動かしてかけるビブラートです。速いビブラートをかける際に重宝します。バイオリンの先生によってはこの手首からかけるビブラートしか教えない先生もいらっしゃいます。
腕でかけるビブラート
腕でかけるビブラートは腕を振るイメージでゆっくりかけるビブラートです。主に遅いビブラートをかけるのに役立ち、ビオラでは速いビブラートがあまり必要ないためビオラ奏者は腕でかける人がほとんどです。
バイオリン奏者も腕でしかビブラートをかけない方もいらっしゃいます。私は一番このビブラートを使っており、どうしても腕で間に合わないビブラートを使いたい時に手首でのビブラートを使っています。
正しいビブラートとは
それでは正しいビブラートとはなんでしょうか。
正しいビブラートとは必ず何回入れているか、自覚しながらかけることができているビブラートです。そしてかかっている回数を自覚しながら美しく音楽と伴ってかけることができるビブラートです。
速すぎる人は痙攣のようなビブラートになっている人も多く、手は動いているのに音を聴くと全くビブラートがかかって聞こえないという人もいます。
と言われた時に速さを変えられるように取得しなければいけません。
また、無意識にかけようと思っていなくても、とにかくどの音にもかかってしまったり、ある一つの指だけ(4の指だけなど)ビブラートがかからないというのもいけません。また指を変える瞬間に毎回止まるビブラートもダメです。
全ての指・腕で自覚を持ってコントロールでき、音楽の表現の手助けになっているのが真の正しいビブラートです。
ビブラートの練習のやり方
それでは、ビブラートの概要がわかったところで、実際にビブラートの練習をしてみましょう。
ロングトーンを軸としたビブラート練習
基本的に、ロングトーンにビブラートを付けて練習していきます。
メトロノームを60に設定して、1音4拍伸ばす要領でそこにビブラートをかけていきます。
まずは、ピッピのタイミングでビブラートを1回だけ。できたらピッの中に2回、できたら4回、8回、16回、というように増やしていきます。
この練習をする時に注意点は3点あります。
- 必ず入れている回数を自覚しながら弾く
- 主軸となっている音程が変わりすぎていないか気にかける
- 基本となる音程から下にかける
特に3つ目の音程よりも下にかけるというのはとても重要です。
上にも下にもビブラートをかけてしまうと、曲全体で聴いた時に車酔いするような演奏になってしまいがちです。自分のビブラートが音程が上に上ずるようにかかってしまっていないかしっかりとチェックしてください。
そしてロングトーンの練習だけでもかなり注意することがありますので、こちらの記事を読んで小野アンナバイオリン教本を使ったロングトーンをしっかりと取得してからビブラートの練習をするようにしてくださいね。
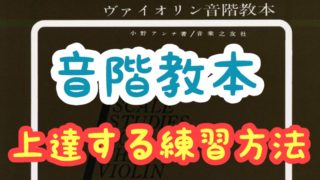
ビブラートの練習の最初でつまずく人は
ビブラートがそもそもかけられない、力が入って動かないという方は、そもそも左手の力が入りすぎです。ネックは絶対に握ってはいけません。
一旦左手を下にぶらんと下げて力を抜きます。そのままの脱力した状態で手を上に向けて構えるようにしてください。おさえる際も本当に最小限の力です。
またビブラートの雰囲気を全く掴めない方はこちらの動画に良い練習が載っていましたので、参考にされると良いです。
練習の際は必ず動画のようにハンカチなどで押さえて、楽器を傷つけないように気をつけましょう。
ビブラートのまとめ
ビブラートってかけられるようになると表現の幅が広がってとても楽しみも広がりますが、奥も深いですよね。